2025年 4月27日(日)、六本木「ストライプハウスギャラリー スペースD」での『ダンスの犬ALL IS FULL ブレイン・ロット うすい風 脳の腐敗からの(深谷正子演出・振付)』公演。立ち会いの記録「見たこと、感じたこと、考えたこと」。
この記事は公演中に私の頭の中で浮かんだこと、振り返りからの再確認、公演前後の雰囲気や空気感なども含めながら書き殴った記録的な文章。ライブ感をできるだけ残したいので、時間経過に重きをおいている。一気に書き上げる時間がないため、何度かに分けて追記していく。いままで完結せずに終わったまま放置している投稿も多いが、メモは残しているので、すべてしっかり書き残しておきたい。
文章は冗長気味で、わかりにくい表現も多い。しかし、「書くこと(伝えること)に意義あり!」のスタンス。そこには異議は認めないが、文章の批判は大歓迎。
公演の画像が気になる方は、facebookで「ブレイン・ロット」「P’Lush」あたりで検索してもらうと出てくるはず。
・ ・ ・
今回の公演は深谷正子さんの演出・振付による「デュオ3作品」「トリオ1作品」の連作。4作品ともコンセプトは同じもので、演じ手によって変化が楽しめる内容。残念ながら私は最終日の「トリオ1作品」だけを拝見。
拝見するにあたっての私的な予想?なども含めて 公演紹介を投稿していたので、貼っておく。
『ダンスの犬ALL IS FULL ブレイン・ロット うすい風 脳の腐敗からの(深谷正子演出・振付)』〜 4月26・27日開催 六本木「ストライプハウスギャラリー」にて
https://heart-to-art.net/improart/blogtitle2025-026-fukaya/
[template id=”2416″]
公演前に感じていたこと
今回は紹介記事でも書いたとおり、深谷さんご自身の<在り方>を「デュオ」「トリオ」という形態によって表現しようとする試みだと勝手に想像していた。
結論から言ってしまうと、4公演とも同じ設定で、あとは演者のポテンシャルに委ねた公演だったようだ。
公演終了後の挨拶で深谷さんは「若手への希望を託した公演。ひとつのキーワードを4つに分化させたもので、初めての試みだった」と話されていたが、深谷さん本人は満足のいく結果となったと思われる。
シリーズ出演者の方々
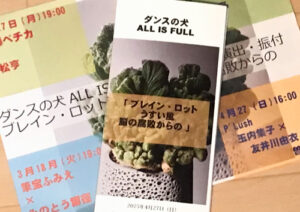
紹介記事と重複するが、まずは出演者を記しておく。
・3月17日 佐藤ペチカさん・小松亨さん
・3月18日 筆宝ふみえさん・みのとう爾徑さん
・4月26日 斉藤直子さん・秦真紀子さん
・4月27日 玉内集子さん・友井川由衣さん・曽我類子さん
共通した小道具「綿」

4回を通じて使われた小道具は、大量の「綿」。演者は綿をどのように解釈し、どう表現していくかが主題のひとつだったと思われる。
表現方法としては、衣装の中に詰め込んだり出したりといった作業は共通だったようだ。綿で膨れ上がって異形化した人間(物体)は視覚的に面白いのは言うまでもない。
肝心なのは演者や見る側の綿に対するイメージ。
イメージの持ち方によって、感想も大きく変わってくるものとなる。
綿のイメージは限りなく浮かんでくる。
パッと思いつく言葉を列記すると、「純粋さ」「曖昧さ」「優しさ」「幻想」「魂の欠片」「記憶の断片」「感情の塊」「運命」「静寂」「癒し」「執着」「純粋」「包み込む存在」「中身を詰める素材」「浮遊」などなど。
きっと4回それぞれに演者は別のイメージで公演に臨んだのだろう。
コンタクトから見える演者同士の「在り方」
今回の公演では、コンタクトも気になるポイントだった。2人ないし3人だからこそ生み出すことができる組み合わせの動き(会話? 対話?)をどう料理していくのか?
コンタクトを通じ、予定調和ではない演者同士の「在り方」がどう見えてくるのかが楽しみのひとつだった。
タイトルについて
今回の公演タイトルは「ブレイン・ロット うすい風 脳の腐敗からの」。
これを見たときに、私は「???」と思ってしまった。
ブレイン・ロットは2024年に話題となった言葉。SNSなどで脳が劣化(腐敗)してしまった状態を示すもの。オックスフォード大学出版局が「Oxford Word of the Year(今年の言葉)」に選んだことでも知られている。
しかし、ブレイン・ロットは新しい言葉ではない。調べてみると、1854年に出版されたアメリカの超絶主義の作家ヘンリー・デイヴィッド・ソローによる著作『ウォールデン 森の生活』(←クリックするとAmazonのページに飛びます)が原点となる言葉だった。ソローは1840年代のジャガイモ不作の飢餓状態「ポテト・ロッド」になぞらえてブレイン・ロットという言葉を生み出した。
超絶主義というのは、「個人の自由や自立、自然との一体感を重視する主張」であり、「自然と接触し、自然との一体感によって真理を認識できる」と考えた思想。
ソローは文明(資本主義)の発達によってジャガイモ腐れのように人間の脳も腐ってしまう危機感を覚えたようだ。そして1万年以上も前に氷河によってできたウォールデン池畔へと移り住んだ。『ウォールデン 森の生活』は、ソローが約2年ほど自然の中で暮らした経験が記されたものとなっている。内容的には自然回帰というより、「個の確立」をめざしたものであった。
深谷さんがソローを意識されたのかどうかはわからない。「うすい風」という言葉を使ったのは、本能的に真理を理解する触媒として「自然」をイメージしたからなのかもしれない。同時に、深谷さんが何らかの危機感を抱いていることも想像できる。言うなれば「ダンス・ロッド」ともいえるだろうか。
前置きが長くなってしまった。ここからが公演の感想。
今回はここまで。続きは、また! (2025/05/03)
※一気書きしているので、加筆修正することもあります。どうぞご了解ください。
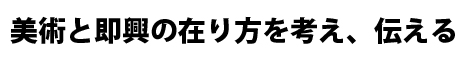

コメント